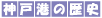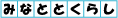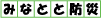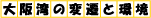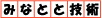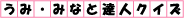慶応3年(1868年)12月7日、兵庫港開港となりました。
当初、幕府が諸外国との間に調印した「修好通商条約」で
決められた開港地は兵庫津が対象でした。
市街地に近い和田岬から妙法寺川尻に至る臨海部を外国人居留地とし、
沖合いに防波堤を築いて内側を開港場とする計画だったようです。
しかし、四ヶ国連合艦隊が兵庫に来た際に付近の海域を測量した結果、
英国公使パークスは兵庫港より神戸の入り江の方が港に適していると判断し、
その後方の土地が居留地に選定されたのです。
居留地に選定された鯉川から生田川の間の土地は兵庫でなく神戸村に属していました。
当時外国人は、神戸も兵庫の一部と思っていたか、
幕府がそのように説明していたのではないかと考えられています。
開港後も公文書には「兵庫居留地」と記されています。
しかし、「天然のすぐれた投錨地となっている小さな湾」
と言う表現から神戸をさしていることは間違いありません。
こうして開港地が兵庫から神戸になったのです。
その後、明治25年(1892年)勅令により「神戸港」となると、
急速に近代化し、人・物・情報が行き交う拠点として、また、国際貿易港として、
世界を代表する港に発展しました。 |