|
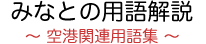 |
|
| D |
 |
dB(A)・EPNL・WECPNL |
 |
| |
dB(A)は、騒音レベルの大きさの単位であり、人間の騒音の大きさに対する感覚に近い周波数補正特性のAを用いて測定されたものをいう。
・EPNL (Effective Perceived Noise Level:実効感覚騒音レベル)は、航空機騒音測定のために考案されたもので、航空機騒音の特異音や継続時間の違いによるうるささを評価するための尺度である。
・WECPNL (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level:加重等価平均感覚騒音レベル)は、通過全航空機の騒音を夕方及び夜間の分を加重してたしあわせ、1日あたりの騒音のうるささを評価する尺度である。 |
 |
DME (Distance Measuring Equipment) |
 |
| |
距離情報提供装置のことで、電波の伝搬速度が一定であることを利用し、航空機から地上のDME局へ距離質問電波を発射し、それに応じてDME局から発射された応答電波を受信するまでの時間的経過から地上局までの距離を連続測定できる。 |
 |
DTAX (Domestic Telecommunication Automatic
Exchange and Aeronautical Data Processing System) |
 |
| |
国内航空交通情報処理中継システムのことで、航空交通情報システムにおける通信センターとして、各空港等に設置されたデータ端末等と情報通信ネットワークを形成し、航空機の運航に必要な各種情報の処理中継を行っている。 |
 |
FDP (Flight Data Processing System) |
 |
| |
飛行計画情報処理システムのことで、飛行計画報(フライトプラン)、出発報等航空機の運航に関する情報を電子計算機で処理し、管制官に運航票等を自動的に印刷、配布するほか、RDP、ARTS等の他システムに対し飛行計画データを提供するシステムである。 |
 |
FIR (Flight Information Region) |
 |
| |
飛行情報区のことで、各国が航空交通業務を担当する区域を示し、ICAOで決定される。通常、自国の領空に隣接する公海の上空を含む。日本は東京FIR及び那覇FIRを担当している。 |
 |
FSC (Flight Service Center:飛行援助センター) |
 |
| |
航空機の航行に必要な情報の収集及び対空通信による提供、航空機の運航の監視等、航空機の安全かつ円滑な運航を24時間支援する機関。 |
 |
GCA (Ground Controlled Approach) |
 |
| |
着陸誘導管制所のことで、ASR(空港監視レーダー)及びPAR(精密進入レーダー)を使用して計器飛行方式により飛行する航空機に対して、管制官が無線電話により針路、高度の指示を発出し、誘導して着陸させる着陸誘導管制業務を行う機関である。 |
 |
IATA (International Air Transport Association) |
 |
| |
国際航空運送協会のことで、1945年、各国定期国際航空会社を会員として結成された団体である。安全、定期的かつ経済的な航空運送を助成し、国際航空業務に従事する航空企業が互いに擁力することを目的とし、特にその運送会議で、国際運賃水準の設定を行っている。1979年10月、組織を改革し、従来に比べ、弾力的な運賃設定方式を確立した。本部はモントリオール及びジュネーブにあり、1997年6月現在、会員数は255社(正会員217社、準会員38社)。日本からは、日本航空、全日本空輸、日本エアシステム、日本貨物航空が正会員として参加している。 |
 |
ICAO (International Civil Aviation Organization) |
 |
| |
国際民間航空機関のことで、1944年の国際民間航空条約(シカゴ条約)に基づいて設立された国連の専門機関の一つである。国際民間航空の安全かつ秩序ある発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を図ることを目的とし、技術的問題、法律的問題等に関する各種の活動のほか、最近では経済的問題に関する活動も行っている。本部はモントリオールにあり、2002年6月現在、188ヶ国が加盟している(日本は1953年10月に加盟)。 |
 |
IFR・VFR |
 |
| |
IFR (Instrument Flight Rules:計器飛行方式)は、航空機の飛行経路や飛行の方法について常時航空交通管制の指示を受けつつ飛行することをいい、VFR
(Visual Flight Rules :有視界飛行方式)は、有視界気象状態(VMC)において、原則として航空交通管制の指示を受けず操縦者の独自の判断で飛行することをいう。 |
 |
IIT運貨 (Indivisual Inclusive Tour Fare:個人包括旅行運賃) |
 |
| |
旅行業者が目的地での観光、宿泊等の地上手配を行う、いわゆる包括旅行のための運賃である従来のGIT運賃(団体包括旅行運賃)の最低催行人数の規定が、個人旅行者の増大という市場動向の変化の中で実情に合わなくなったことにより、1人より適用可能な旅行商品造成用の国際運賃として平成6年4月1日より導入された。 |
 |
ILS (Instrument Landing System) |
 |
| |
計器着陸装置のことで、着陸する航空機に対して空港に設置されたILS地上施設から、進入方向と降下経路を示す二種類の誘導電波を発射し、パイロットは悪天侯時においても、ILSの電波を受信し機内の計器を見つつ操縦することにより、所定のコースにそった安全な着陸を可能とする着陸援助施設である。 |
 |
IMC・VMC |
 |
| |
VMC (Visual Meteorological Condition:有視界気象状態)とは、操縦者が目視により飛行するのに十分な視程(目視できる最大距離)及び航空機から雲までの距離を考慮して、航空機の飛行する高度と空域別に定めた下表以外の気象状態をいい、それ以外の気象状態をIMC
(Instrument Meteorological Condition:計器気象状態)という。 |
 |
INS (Inertial Navigation System) |
 |
| |
慣性航法装置のことで、航空機の加速度を積分計算し、速度と移動距離を得、航空機の位置、目的地までの距離、飛行時間等航法上必要な資料を得る自蔵航法装置である。 |
 |
ITC (Inclusive Tour Charter) |
 |
| |
地上部分におけるツアー等と航空運送とを組み合わせた包括旅行チャーターのことである。国際旅客の運送に係るチャーターの類型が我が国において認められているものには、このほか、アフィニティーグループチャーター(旅行の実施以外を目的とする類縁団体のためのチャーター)とオウンユースチャーター(個入・会社等が航空機1機を貸切り、これをその顧客等に利用させるためのチャーター)があるが、ITCは特に一般公募が可能であるという点で、これら二つのチャーターと異なっている。 |
|
|