
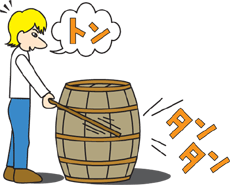
船の大きさを現すとき、載貨(さいか)重量トン、総トンなどの表現が用いられていますが、このトンという単位、じつは酒樽を叩いたときの“トン”という音に由来するというのは、本当の話です。15世紀のはじめの頃、フランスからイギリスへボルドー産のワインを運ぶ船の大きさを表すのに使われ始めたものだといわれています。船にこの酒だるをいくつ積めるか数えるとき、棒で酒だるをたたくと「タン、タン」と音がすることから、それが「トン」に変わっていったというのです。ワインの樽をいくつ積めるかで、船の載貨能力(さいかのうりょく)を示したわけですね。
日本では昔、千石船など積む事ができる米の石数であらわしていました。お米の量を「石(こく)」と呼んでいたのです。しかし、明治時代になって海外からいろんな荷物が来るようになり国際化が進んだので、世界と同じ「トン数」を使うようになりました。